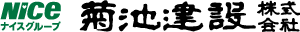匠の技ドキュメント
N様邸 構造材建て込み作業
一般住宅では珍しい、木組みの太鼓梁をふんだんに現わした建物の構造材建て込み作業をご覧頂きます。
社寺建築など大型木造建築物では馴染み深い太鼓梁。伝統建築の木組みを構成する主要な構造材ですが、匠の技が施されているのにも関わらず、完成すると天井裏に隠れてしまい目にすることがありません。 太鼓梁1本1本の自然な曲がり形状を活かし、精緻に組み合わされた木組みのダイナミックな構造美を、そのまま室内意匠として現わす住宅の注文を受けて、社寺建築を手掛ける社員大工チームが施工を担当することになりました。
コンピュータ制御によってプレカット加工された構造材と、木組み構造を現わしにする箇所のみ社員大工によって手刻み加工された構造材、2つを組み合わせて1棟の住宅の骨格を形作る建て込み作業が始まりました。
 静岡市清水区の本社で手刻み加工された太鼓梁が、建築地に向けて出荷される日を迎えました。(平成27年9月28日撮影)
静岡市清水区の本社で手刻み加工された太鼓梁が、建築地に向けて出荷される日を迎えました。(平成27年9月28日撮影) 太鼓梁と共にプレカット工場から持ち込まれた構造材(左奥)も一緒にトレーラーで出荷されました。
太鼓梁と共にプレカット工場から持ち込まれた構造材(左奥)も一緒にトレーラーで出荷されました。 構造材建て込み作業初日の建築現場。奥行きのある建物の内、太鼓梁など手刻みの構造材が組まれるのは画面左手部分。(平成27年10月1日撮影)
構造材建て込み作業初日の建築現場。奥行きのある建物の内、太鼓梁など手刻みの構造材が組まれるのは画面左手部分。(平成27年10月1日撮影) 敷梁(しきばり)の上に、投げ掛け梁を台持ち継ぎで繋ぎ合わせる作業。
敷梁(しきばり)の上に、投げ掛け梁を台持ち継ぎで繋ぎ合わせる作業。 小屋組みの最下層・地廻り(じまわり)の梁が組みあがった現場。
小屋組みの最下層・地廻り(じまわり)の梁が組みあがった現場。 1日目の作業が終了。翌日から地廻りの梁組みの上に、二重・三重の梁小屋組みが作られていきます。
1日目の作業が終了。翌日から地廻りの梁組みの上に、二重・三重の梁小屋組みが作られていきます。 構造材建て込み作業、2日目の建築現場。(平成27年10月2日撮影)
構造材建て込み作業、2日目の建築現場。(平成27年10月2日撮影) 2階床部分には特厚の檜合板が既に張られ、安全な作業足場としても有効利用されています。
2階床部分には特厚の檜合板が既に張られ、安全な作業足場としても有効利用されています。 土台よりも太い直径45センチの丸太柱は「落し蟻」と呼ばれる形状で直接基礎に据え付けられています。
土台よりも太い直径45センチの丸太柱は「落し蟻」と呼ばれる形状で直接基礎に据え付けられています。 2階床梁と化粧太鼓梁を2段で支える丸太柱頭部。
2階床梁と化粧太鼓梁を2段で支える丸太柱頭部。 渡り腮(わたりあご)と呼ばれる仕口(しぐち)で梁を交差させた伝統的な架構が目を引く、1階から見上げる吹き抜けの小屋組み部分。
渡り腮(わたりあご)と呼ばれる仕口(しぐち)で梁を交差させた伝統的な架構が目を引く、1階から見上げる吹き抜けの小屋組み部分。 金物が見えないよう貫通ボルトを使った太鼓梁接合端部。
金物が見えないよう貫通ボルトを使った太鼓梁接合端部。 吹き抜け小屋組みの太鼓梁小屋束立て部分。
吹き抜け小屋組みの太鼓梁小屋束立て部分。 建て込み作業3日目を迎えた建築現場。(平成27年10月3日撮影)
建て込み作業3日目を迎えた建築現場。(平成27年10月3日撮影) 2階床の高さから見る1階吹き抜け小屋組み部分。
2階床の高さから見る1階吹き抜け小屋組み部分。 1階から見上げる吹き抜け小屋組み部分。三重に梁を架け渡した伝統的な和小屋組みが、ダイナミックな空間をつくり上げています。
1階から見上げる吹き抜け小屋組み部分。三重に梁を架け渡した伝統的な和小屋組みが、ダイナミックな空間をつくり上げています。
掲載日 2015.10.20
Copyright © Kikuchi kensetsu Corp. All rights reserved.