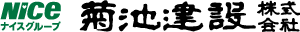匠の技ドキュメント
泉蔵院本堂・新築工事:その9
高野山真言宗・泉蔵院(神奈川県平塚市)本堂建築工事が進んでいます。 構造材には檜や松など、すべて国産材を、さらに目に見える化粧材にはほぼすべて檜を使用するなど、伝統木造建築にふさわしい、上質な木材をふんだんに使った建物になります。
現地での建築工事が始まり、まず最初に屋根をつくり上げていきます。銅板葺きの入母屋屋根に仕上がりますが、寺院ならではの木造装飾物や屋根組構造に一般住宅とは異なる特徴を随所に見ることができます。
 本堂の正面となる西側の外観。(平成23年9月24日撮影)
本堂の正面となる西側の外観。(平成23年9月24日撮影) 南西側から見た本堂外観。
南西側から見た本堂外観。 外周廻りの柱には、土台と平行して「足固め」と呼ばれる貫材が柱の足元を繋ぎとめています。
外周廻りの柱には、土台と平行して「足固め」と呼ばれる貫材が柱の足元を繋ぎとめています。 足固めは柱の向う側から差し込まれた竿を2箇所の「車知栓(しゃちせん)」と呼ばれる木組みで固定されます。
足固めは柱の向う側から差し込まれた竿を2箇所の「車知栓(しゃちせん)」と呼ばれる木組みで固定されます。 屋根軒先を支える「桔木(はねぎ)」が建物周囲にせり出し、屋根型の雰囲気が分かります。
屋根軒先を支える「桔木(はねぎ)」が建物周囲にせり出し、屋根型の雰囲気が分かります。 外観の中でも最も寺院らしい意匠の一つ、軒下の組み物部分。
外観の中でも最も寺院らしい意匠の一つ、軒下の組み物部分。 太鼓挽きの材料の上に角材の母屋が組み上げられ、入母屋の屋根型が現れ始めます。
太鼓挽きの材料の上に角材の母屋が組み上げられ、入母屋の屋根型が現れ始めます。 建物の四方向すべての軒先を支える「桔木」には、上下面に丸身の残った太鼓挽き材を使用。
建物の四方向すべての軒先を支える「桔木」には、上下面に丸身の残った太鼓挽き材を使用。 「桔木」はテコと同じ原理で、軒先を内側で跳ね上げて支えています。
「桔木」はテコと同じ原理で、軒先を内側で跳ね上げて支えています。 軒先までの傾斜や跳ね出し量に応じて、テコの力点にあたる「桔木」の固定位置が異なります。
軒先までの傾斜や跳ね出し量に応じて、テコの力点にあたる「桔木」の固定位置が異なります。 角材の敷梁(しきばり)の上で、左右から架け渡された太鼓梁が「台持ち(だいもち)」継ぎされた小屋組の納まり。
角材の敷梁(しきばり)の上で、左右から架け渡された太鼓梁が「台持ち(だいもち)」継ぎされた小屋組の納まり。 本堂内部、唐草模様の虹梁(こうりょう)を間近に見ることができるのも作業足場がある期間ならでは。
本堂内部、唐草模様の虹梁(こうりょう)を間近に見ることができるのも作業足場がある期間ならでは。
掲載日 2011.11.14
Copyright © Kikuchi kensetsu Corp. All rights reserved.