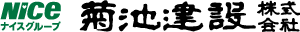匠の技ドキュメント
泉蔵院本堂・新築工事:その8
高野山真言宗・泉蔵院(神奈川県平塚市)本堂建築工事が進んでいます。 構造材には檜や松など、すべて国産材を、さらに目に見える化粧材にはほぼすべて檜を使用するなど、伝統木造建築にふさわしい、上質な木材をふんだんに使った建物になります。
上棟式に向けて建て方が始まりました。一般住宅とは異なる複雑な構造体であるため、建て方の手順にも細心の注意が必要です。構造体がそのまま意匠となる寺院建築ならではの建て方作業風景をご紹介します。
 建て方に先立ち足場が組まれた建築現場。土台も既に設置され雨除けのブルーシートで養生されています。(平成23年8月29日撮影)
建て方に先立ち足場が組まれた建築現場。土台も既に設置され雨除けのブルーシートで養生されています。(平成23年8月29日撮影) 虹梁(こうりょう)で繋がれた2本の丸柱が吊り込まれていきます。
虹梁(こうりょう)で繋がれた2本の丸柱が吊り込まれていきます。 吊り込まれる丸柱の足元部分。土台の間に「落とし蟻」で建て込み、基礎に直接柱が自立する構造です。
吊り込まれる丸柱の足元部分。土台の間に「落とし蟻」で建て込み、基礎に直接柱が自立する構造です。 外周廻りの基礎には御影石の布石が並べられ、耐震性能を確保しながらも寺院に相応しい伝統的な意匠に仕上げられています。
外周廻りの基礎には御影石の布石が並べられ、耐震性能を確保しながらも寺院に相応しい伝統的な意匠に仕上げられています。 建て方の合間を縫って、向拝の柱の独立基礎石をレッカーを使って設置していきます。
建て方の合間を縫って、向拝の柱の独立基礎石をレッカーを使って設置していきます。 設置の終わった向拝の柱基礎石。中心に柱を固定するアンカーボルトが見えます。
設置の終わった向拝の柱基礎石。中心に柱を固定するアンカーボルトが見えます。 本堂の柱がすべて建て込まれ、柱頭が梁桁で繋がれた状態。見えている構造材はすべて化粧材なので雨濡れを防ぐ養生をしながらの建築作業が続きます。(平成23年9月7日撮影)
本堂の柱がすべて建て込まれ、柱頭が梁桁で繋がれた状態。見えている構造材はすべて化粧材なので雨濡れを防ぐ養生をしながらの建築作業が続きます。(平成23年9月7日撮影) 寺院ならではの組みものの一つ「三斗(みと)」を組み立てています。(平成23年9月12日撮影)
寺院ならではの組みものの一つ「三斗(みと)」を組み立てています。(平成23年9月12日撮影) 外周廻りの柱頭すべてに肘木を十字に組み、三斗を載せて「出三斗(でみと)」をつくっていきます。
外周廻りの柱頭すべてに肘木を十字に組み、三斗を載せて「出三斗(でみと)」をつくっていきます。 外周廻りの組みものが一通り出来上がり、化粧垂木を受ける丸桁(がんぎょう)が載せられました(平成23年9月15日撮影)
外周廻りの組みものが一通り出来上がり、化粧垂木を受ける丸桁(がんぎょう)が載せられました(平成23年9月15日撮影) 本堂内部に掛け渡された唐草模様の彫刻が施された虹梁。寺院建築ならではの特徴ある意匠です。
本堂内部に掛け渡された唐草模様の彫刻が施された虹梁。寺院建築ならではの特徴ある意匠です。 本堂の大屋根を支える太鼓梁が掛け渡され、小屋組みの施工が始まります。
本堂の大屋根を支える太鼓梁が掛け渡され、小屋組みの施工が始まります。
掲載日 2011.10.26
Copyright © Kikuchi kensetsu Corp. All rights reserved.